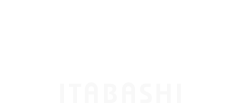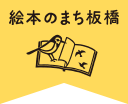成増小学校(令和7年7月3日訪問)
教育長訪問記
7月3日(木曜日)成増小学校を訪問しました。教育長ふらっと訪問になります。
本校は「考え行動する 役に立つ つながる きたえる」という自立・貢献・共生・健康を教育目標にしている小学校です。令和7年度の校内研究の主題は「自分で選び、より良くしようとする児童の育成 ~START 個別最適な学び How to do?~」を掲げています。
早速、小松校長に案内されて全学級の授業を見て回りましたが、本校では校内研究の主題にあるように、積極的に「板橋区授業スタンダードS」に取り組んでいるとのことです。この授業スタンダードSとは、児童生徒の自己(Self)、選択(Select)の場面を取り入れ、自分の選んだ内容、方法、ペースなどで学習する、自己調整型学習の授業スタイルの板橋区での呼称です。私が教育長として令和6年7月に着任してから推奨しています。教材や単元、発達段階に応じて自己決定、自己選択、自己調整する範囲を設定します。

例えば、上の写真は研究主任の学級の社会科の授業です。調べたり探究したりする課題に対して、誰とどのように学習するのかは、児童が自分で選択して進めていきます。黒板には児童の名前のマグネットシートがあり、各自がどの課題に取り組んでいるのか、先生や他の児童にもわかるようになっています。教室の前方には個人で学習する児童が、一人一台端末で調べたり、ノートに記入したりしていました。

先生は上の写真のように、教室を回って必要な助言指導をしています。児童の個別の学習状況を把握することができ、その子にあった適切な助言ができます。この自己調整型の学習では、先生が一斉に説明する時間は極力短くして、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図っているのです。誤解のないように説明すると、先生が説明する時間がないわけではありません。児童が個別で進める時間を確保するからこそ、一斉での説明(特に授業の最初と終わり)は重要になります。放任して自由に学ぶということではありませんし、先生が指導しないわけでもありません。むしろしっかり指導していく取り組みになります。授業スタンダードSの授業に誤解が生じないようにしたいものです。

教室の後方では、上の写真のようにグループで学ぶ児童が集まっていました。3つか4つのグループがあり、ちょうどグループ内で発表する時間で、一人の児童が立ち上がって説明しているところです。このあと、質問しあう時間へと続きます。
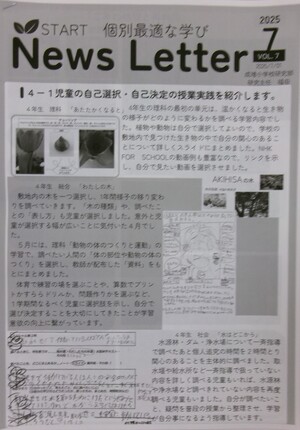
このような授業の成果をまとめ、先生方が相互に学び合うため、上の写真のように研究主任の先生が「個別最適な学び News Letter」というのを作成していました。どのような取り組みが有効なのか成果を積み上げていくとともに、課題を整理して改善する研究を進めているとのことです。
先月(6月)から、全ての区立幼稚園・小学校・中学校の校長先生(75人)と面談していますが、多くの学校が板橋区授業スタンダードSに取り組んでいることがわかりました。この板橋区授業スタンダードSは、普通の授業スタンダードとは異なり、各学校では全教員が取り組まなくてもよいという方針で、つまり先生自身もこの方法を取り入れるかどうかを選択(Select)できるというわけです。最近、区別するために、従来からの授業スタンダードを「授業スタンダードB」と呼んでいる学校もあります。Bはベーシック(Basic)の頭文字です。

上の写真は、別の学級の図工の授業です。児童が夢中になって作品づくりに取り組んでいることがわかります。児童は1単元時間ではなく、何時間か使って、自分のペースで自分の作品を仕上げていきます。そう考えると図工の学習は、もともと授業スタンダードSを実践していたことになります。
本校のこれからの実践と研究に期待しています。個別最適な学びが研究主題になっていますが、それと協働的な学びとをどう結びつけるか(融合させるか)が鍵だと思います。集団のあり方や学級経営とも連動しています。
(記・長沼豊教育長)
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。